日本女性会議 参加報告(2012年~2017年)
更新日:2019年8月29日
日本女性会議2017とまこまい 参加報告
男女共同参画市民研修「日本女性会議2017とまこまい」(平成29年10月13日(金曜日)~14日(土曜日))に2人が参加しました。研修の中で全国の皆さんと交流しながら、女性の社会的地位の向上や男女共同参画の実践・実現について学んだことを報告します。
報告者 志岐 玲子さん
研修概要
記念講演で女優・渡辺えりさんは、男性中心の劇作家の世界で、どれほど厳しい体験をしたかを語られた。武川恵子内閣府男女共同参画局長が基調報告の中で、「世界各国でペナルティのついた取り組みが効果をあげている」と述べられた。議員についても「クオータ制」の導入によって女性議員が増えている。 街づくりや災害時の避難所運営に女性の視点が必要だといわれている。日常の暮らしの中に、女性の視点を取り入れた取り組みが当たり前になされている状況があってこそ、いざというときにもその本領が発揮される。私たち自身がもっと積極的に様々な場に参画していくことが課題だと思った。 今、私は大野城市内で、仲間とともに地域の子どもたちの学習支援に 取り組み始めた。2日目の第5分科会「子どもの貧困~貧困に悩む子ど もたち 皆でなくそう貧困の連鎖を~」シンポジウムに参加し、居場所・学習・食それぞれの観点からの取り組み報告を聴いた。そこで、子どもたちが安心して過ごし、生きる力を身につけ健やかに成長していくことができる環境づくりのノウハウ等を学ぶことができた。
感想・今後の活動
特別揮毫(きごう)・講演で、書家・金澤翔子さんの揮毫の後、母・金澤泰子さん(東京藝術大学評議員、日本福祉大学客員教授)が「ちがいはかけがえのない個性~ダウン症の娘と共に生きて~」と題して講演された。「翔子が一人暮らしを始めてから、『障がい』があるからできないと、親の独善で決め付けてきたことがたくさんあることに気づいた」と述べられたことが印象に残った。地域活動の中で、子どもや障がい者、高齢者等さまざまな人と接するときに、それぞれの個性を生かし自立を支援していくことが課題なのだと学ぶことができた。
報告者 早瀬 ひろ子さん
研修概要
10月13日から14日にかけて、北海道苫小牧市で開催された、第34回日本女性会議に参加して来ました。日本女性会議は、1975年の「国際婦人年」とこれに続く「国際婦人の10年」を契機に男女が共に支えあう社会を築くことを目的として、昭和59年(1984年)から毎年各都市で開催されているものです。
イランカラプテ(アイヌ語で「こんにちは」を意味するおもてなしの言葉)に迎えられた「日本女性会議2017とまこまい」のテーマは「北の大地で語ろう これからの未来の一歩を」でした。参加者2,000人。合言葉は「市民・団体の力+企業の力+行政の力=オールとまこまい」。800人のボランティアがオレンジ色に身を包み、道案内や会場案内その他の役割をテキパキとこなされている姿に、大会を成功させようという意気込みと熱意を感じました。
さて、1日目の特別揮毫(きごう)・講演ではダウン症という障がいを持って生まれながら、現在書家として大活躍の金澤翔子さんが壇上で『共に生きる』と揮毫され、お母様の泰子さんから今日に至るまでの壮絶なお話を伺いました。マイケルジャクソンが大好きで、ちょっとお茶目な翔子さんは、周りの人たちに優しい光と愛を注ぐ女性に成長されました。30歳の時に一人暮らしを始め、食事、買い物、身のまわりの事、そしてお金の管理までご自分でされているそうです。NHK大河ドラマ「平清盛」の題字を書かれた翔子さんとご紹介すれば、彼女を身近に感じていただけるのではないかと思います。違いはかけがえのない個性。生きてさえいれば絶望は無い。障がいとは何か、違いとは何かを考えさせられました。
2日目は11ある分科会のテーマの中から「今、個性を認め、未来を育む教育とは何か?」というテーマの「教育」を選びました。この分科会のパネリストの一人に加藤久美子さんがおられました。彼女の四男が、骨形成不全の症状で障がいがあると分かり、手術を繰り返すという怒涛の日々を送られる中、子どもの成長と共に色々な問題に直面されたそうです。そこで多くの活動を始められました。現在、「NPO法人障がい児の積極的な活動を支援する会にわとりクラブ」の副理事長をされながら、障がいのある子もない子もごちゃまぜで活動する機会を作ってあります。親子で問題に取り組み克服された加藤さんは、「個性や多様性が認められる世の中になってほしい。障がいも左利きと同じように個性です」と結ばれました。
感想・今後の活動
障がいのある人やその家族が、我慢や、微妙な空気を読んで生活することなく、一人ひとりの個性として認められ、尊重される社会になることを私も願っています。貴重な機会を与えていただき本当にありがとうございました。
日本女性会議2016秋田 参加報告
男女共同参画市民研修「日本女性会議2016秋田」(平成28年10月28日(金曜日)から30日(日曜日))に2人が参加しました。研修の中で全国の皆さんと交流しながら、女性の社会的地位の向上や男女共同参画の実践・実現について学んだことを報告します。
報告者 石丸 礼子さん
研修概要
研修テーマは「みつめて みとめて あなたと私~多様性(ダイバーシティ)とは~」。様々な思いや考えの違いを尊重して受け入れ、性別や年齢、職業、国籍、障がいなどをこえて、一人ひとりが安心してありたい姿でいることができる、多様性をみとめる社会をつくるため、いま行動したいという思いがこめられています。 一日目は「男女共同参画施策の現状と今後の課題」について、内閣府男女共同参画局長の武川恵子氏より基調報告がありました。男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、将来に夢や希望を持ち、誰もが安心して暮らすことができる地域づくりを進める上で必要不可欠です。平成28年4月に「女性活躍推進法」が完全施行されたことにより、企業・団体・国における女性の積極的な採用、登用が増していくと思われます。 二日目は、8テーマ10分科会があり、私は「人権」のテーマを選択しました。講師は認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク理事長の上野千鶴子氏。男女が共に社会を支えているにも関わらず、意思決定の場には女性が極端に少なく、性別役割分業意識もなかなか変わらない状況で、個人が尊重され、社会的弱者になっても尊厳をもって生き続けられる社会とはどのような社会なのか、自分らしく暮らしていける社会をどのように築いていくのか、20~40代の方の現場の声を交えながらの対談形式で、未来を一緒に考えていこうという内容でした。
感想・今後の活動
今後に活かしていきたいこと
日本女性会議に参加させていただいたことを感謝いたします。今、私達が向き合わなければならない様々な課題に対し、積極的に活動し、活躍されているゲストの方々の貴重な講話を拝聴させていただき、この体験を今後、身近な暮らしの場である地域における男女共同参画・女性活躍の推進に寄与できるよう、自己研鑽に努め活動に活かしていきたいと思います。
報告者 松田 知子さん
研修概要
みつめて みとめて あなたと私~多様性(ダイバーシティ)とは~」というテーマに魅かれて、40歳を過ぎて結婚・出産を経験した今、これからの生きるヒントを学びたいと思い、2歳の息子と一緒に日本女性会議へ参加しました。
秋田へは往復とも羽田空港乗り継ぎの飛行機を利用しましたが、幼児との長時間の二人旅は大変ハードでした。偶然、沖縄県名護市から6名のグループで日本女性会議に参加する方達が隣の席に座られていて、翌日午前中のエクスカーションでも再びご一緒し、息子にも優しく話しかけて下さったり、荷物を持って下さったりして、とても和やかな雰囲気で秋田市内を散策することができました。
1日目は開会式、基調報告に、講師にヘアメイクアップアーティストの藤原美智子さんを迎えての記念講演がありました。藤原さんの「27歳の時に隣の芝生を見るのをやめて自分の個性を確立させることにした」「自分の個性をみとめると自信が生まれて、自分にも他人にもやさしくなれる。すると、他人を受け入れることができるようになった」という言葉が印象的でした。
2日目はテーマ別の分科会、シンポジウム、閉会式があり、私は子育てをテーマにした分科会に参加して全国でも学力トップクラスの秋田での取り組みを学びました。早寝早起き朝ごはん、元気なあいさつ、読んで話して問題解決、子どもが主体という合言葉と、子どもたちが「自分が大事にされている」と感じるように大人が接することが最も重要だと強調されていました。
感想・今後の活動
今後に活かしていきたいこと
今回の研修で学んだことを自分の子育てを通じて大野城市の男女共同参画、そして青少年育成に積極的に参加することで還元していきたいです。
日本女性会議2015倉敷 参加報告
男女共同参画市民研修「日本女性会議2015倉敷」(平成27年10月9日(金曜日)から11日(日曜日))に2人が参加しました。研修の中で全国の皆さんと交流しながら、女性の社会的地位の向上や男女共同参画の実践・実現について学んだことを報告します。
報告者 廣保 晴美さん
研修概要
県下でも先進的な取り組みを行っている大野城市の一員として、大きな流れの中で今後の「男女共同参画」の在り方がどうあればよいのか、今後どのような視点で参画していけばいいのかを学ぶことができればと思い参加しました。
ライフスタイルや価値観が多様化する現代は、仕事・子育て・介護などそれぞれのライフステージにおいて変化を続けています。記念シンポジウム「希望の社会は”わたしたち”にある~ライフステージとそれぞれの男女共同参画~」では、「誰もが輝ける働き方は?」「女性も男性も自信と誇りを持って活躍できる社会とは?」について話し合われました。各分野で活躍するパネリスト・コーディネーターの取り組みや生き方から「希望の社会」と「これからのわたしたち」について意見を伺い、今後のワークスタイルを学ぶことができました。子連れワークスタイルを提唱されたモーハウス経営の光畑由佳さん、ワークライフバランス・ダイバーシティに取り組む企業の取組推進をサポートし、自身が職業人・家庭人・地域人を実践しておられる渥美由喜さん、女性市長で「子育てするなら倉敷で」と言われるまちづくりを実践されている伊藤香織さん。どの発表も人として活き活きと輝き、未来を指し示すものでした。
感想・今後の活動
今後に活かしていきたいこと
- 自分の生き方を見つめ、自己実現を図るためのワークスタイルを考えていけるようにしたいです。
- 仕事・子育て・介護等のサポートができる体制づくりを考えていきたいです。
- 教育の現場、家庭での在り方
- 地域に関わり、地域に必要なサポートの推進
- 行政の地域懇談会に参加し、大野城市に必要なサポート体制の共通理解を図ったサポート
報告者 鬼塚 文子さん
研修概要
1日目は「日本の男女共同参画施策と今後の課題について」の基調報告・記念講演があり、得に上田紀行氏の演題「パッとしない私が、これじゃ終われないと思ったときのこと」はユニークな内容にも、心温まるエピソードを盛り込まれ、話の中に吸い込まれるかのように聞き入りました。
2日目の分科会は、瀬地山角教授による「若者の性行動・性意識をどうとらえるか」の演題で、今や若者の性行動は大きく変化しているといった内容でした。実は第三希望の分科会参加でしたが、データを分析し、グラフ化してあり、大変分かり易い説明でした。”知識なく性に直面する矛盾を解く対策”に、年代差のある私にとって新たな考えを意識できました。
3日目には、良寛和尚ゆかりの円通寺を見学し、歴史の深さを知り、有意義かつ充実した3日間でした。
感想・今後の活動
大野城市の啓発サポーターとして9年目となりますが、「日本女性会議」という大イベントにご縁を繋いでいただいたことにまず感謝いたします。
日本全国の勤勉なる人達と絆を結び、また、他県の方と触れ合い、友を得られたことは、私の今後の大きな財産だと思います。2日間の講演を聞き漏らしてはならないとアンテナを張り参加しましたが、「思いやり・男女が集う・白壁のまち」のテーマの如く、感動の3日間でした。人として知識を得て研鑽していくことの大切さを身にしみて感じ入りました。倉敷市のまちをあげての”おもてなし”、そして男女が出来ることから協力し、助け合い、一人一人が輝くということは、正に共存共栄への第一歩だと確信いたしました。今後の啓発サポーターとしての活動に活かしていかなければと思っています。
日本女性会議2014札幌 参加報告
平成26年5月、6月に募集した男女共同参画市民研修「日本女性会議2014札幌」(10月17日(金曜日)から18日(土曜日))に甲斐理恵さんが参加しました。研修の中で全国の皆さんと交流しながら、女性の社会的地位の向上や男女共同参画の実践・実現について学んだことを報告します。

報告者 甲斐 理恵さん(緑ケ丘)
学習した内容のまとめ
「日本女性会議」に参加し、男女共同参画社会の実現に向けた様々な課題解決への取り組みを知り、知識を深める事ができた。国の動向として、今後の国の発展のために、成長戦略の中核に女性が輝く社会実現に向けた政策が位置づけられている。
参加した分科会では、昔ながらの『男性は仕事、女性は家事・育児』という固定的な性別役割分担意識にとらわれず、父親が子育てを担う必要性について学ぶとともに、男性も女性も、ワーク・ライフ・バランスを意識した豊かな人生を送ることを目指し活動されている団体の活動内容を知ることができた。また、北海道で活躍する男女平等社会を推進する組織のワークショップに参加し、地域の中で男女共同参画を進めていく上での問題点、解決策を探るということを体験した。また、他の分科会報告では、アイヌ民族の女性への差別、若者の間でのデートDVの実態について学んだ。柔道家・山口香さんの記念講演では「男性社会」の風潮が色濃く残っていた柔道界で先駆者として活躍し、自らの人生を切り拓いた先輩やご自身の体験談を聞いた。その話は、自分らしく生きることができる「男女共同参画社会」の実現に向けての必要なヒントを与えてくれるものだった。
参加した感想やこれからの男女共同参画にどのように関わっていきたいか...など
私は、仕事と家庭の両立、妊娠・出産を経て、育児(中)、介護を経験し、女性のライフステージにおける問題を感じた。そして、「娘が女性として自分らしく生きられる社会づくりのために動きたい!」と思うようになり、参加応募するきっかけとなった。
研修に参加し、男女共同参画を推進する上で重要なことは『語り合い、違いを理解し、違いを認める、違いに価値を見出す』ことだと感じた。またそれは、平和でやさしい社会実現につながるとも感じられた。そのためには、同じ感覚・考えを持った者同士がネットワークを作り、発言する場を見出し訴え続け、問題解決へ取り組んでいくことが必要だと思った。今回の学びを活かし、まずは家庭から、そして、職場や地域へ発信できるような活動ができたらと思う。
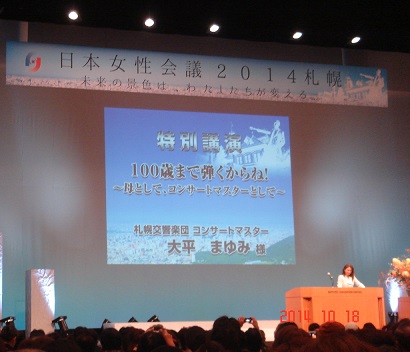
日本女性会議2013あなん参加報告
平成25年5月と6月に募集した男女共同参画市民研修「日本女性会議2013あなん」(平成25年10月11日(金曜日)から12日(土曜日))に、鬼塚春光さん、高木保子さんが参加しました。
研修の中で全国の皆さんと交流しながら、女性の社会的地位の向上や男女共同参画の実践・実現について学んだことを報告します。
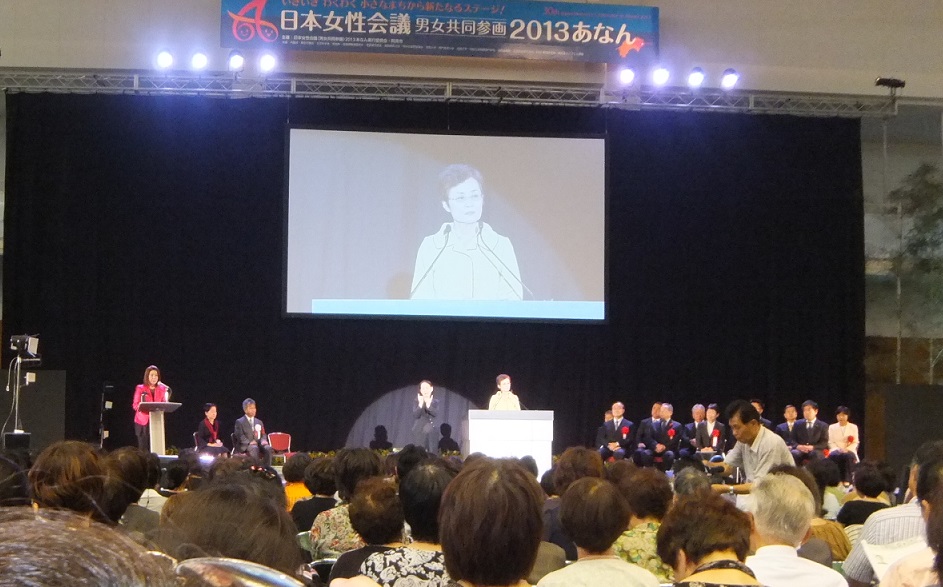
(写真)全大会の様子
- レポート 鬼塚春光さん(PDF:156KB)
学んだ内容のまとめ
分科会においては、阿南地域で活躍しているそれぞれの団体の活動の状況が紹介された。個々の地域興しや自己を高める自主的活動には、私個人の活動に照らし大変興味深く参考にはなったが、本研修の主題である「男女共同参画」という視点からは、いまいち消化不良の感は否めなかった。
また、分科会にしては約200人と多く、呼びかけにあったような「参加する」というのには程遠い感があった。記念シンポジウムは、多くの同種の会議等に参加、傍聴してきたが、近年にない、とても質の高い、内容の濃いものが多いシンポジウムであった。パネリストは、それぞれがいずれも若いのに、多くの経験、実績を持ち、教わることが多かったし、問題提起もしてくれた。
記念講演は、恥ずかしながら私自身よく知らない講師であったが、とても有名で、マスコミにもよく登場してある著名な方だそうで、話の内容は抜群に面白く、また押し付けがましくなく、しかし、しっかりと男女共同参画を説く、とても勉強になるお話で感服させられた。
参加の感想と今後について
いずれのプログラム、特に記念講演や記念シンポジウムは必ずまた、報告書を読み返したくなる内容であった。このように充実した会議、研修に参加させてもらったことに感謝している。
なお、蛇足であるが、圧巻は(1)阿南市の実に多くのボランティアの人達のお手伝いや、その方々による交流会における全ての料理の手作り等に見られる、手厚い「お持てなし」、(2)随所に見せてくれた「阿波踊り」の壮観さ、(3)徳島県知事の弁舌爽やかな挨拶・・・であった。心に残る研修(会議というより、あきらかに研修)だった。
私の応募の動機である「地域の自治会活動における女性の参加(登用)の先進事例を全国に学びたい。」は、そのような場がなかった事や後述の理由により、残念ながら果たすことができなかったが、それ以上に得たものは大きかった。
今後も、上記目的を追求するために機会があれば、また参加してみたい。ひとつ、反省点は、せっかく本市からも女性の参加者がおられたので、その方たちを通してでも、私の参加の主題について全国の参加者にお話を伺う機会を作りたかった。交流会等で、一人で圧倒的に多い女性の参加者に話しかける勇気がなかった。
- レポート 高木保子さん(PDF:124KB)
学んだ内容のまとめ
今回の第30回目日本女性会議から「男女共同参画」の言葉が明記された。私が選択した第9分科会「DV(ドメスティック・バイオレンス)のない地域づくり~男たちの挑戦」においては、40~50代の男性3人が、パネリストとして登場した。DVとは身体的暴力だけでなく、ふつうの夫婦の間にも、支配や暴力が潜んでいて、その原因に性差別が背景にあることに気付いて、相手を尊重するには?家族の人権とは?と考え動き始めたプロジェクトの報告だった。今まで、被害者側からの研修しか受けていなかったので、男性の意識改革が重要だと男性自身が気がついたことに関心した。
翌日の全体会で、徳島県知事から、DVの増加に伴い、こどもと女性の相談を同じ部署に設定、デートDVをアニメ化して、小中高生に教える話があった。また、日本の男女共同参画施策の現状と今後の課題についての報告と、「食育」の講演では、こどもたちに家事をさせて、自立できるように。
また、記念シンポジウムでは4人のパネリストによるトークだったが、その中で、父親から男らしくないと言われて育ち、「らしさ」からの解放を目指し、メンズリブ運動に関わった男性の話が印象的であった。
参加の感想と今後について
田園風景の中にポツンと建物があり、ゆったりとした時間が流れる小さな町徳島県阿南市(人口約8万人)が、全国から2000人以上の参加者を迎えて、会議をどのように運営していくか興味があった。交通、施設等インフラの発達していない中、手作り感とおもてなしの笑顔あふれる会であった。徳島新聞を折ったレジメを入れる袋には、すだちジュースとうちわが入っていて役立った。10月というのに暑かった。阿南駅から全大会のあるスポーツセンターに向かう巡回バスの中から見えたのは、歓迎の文字と20体程のかかし、会場には、折りたたみのパイプ椅子が1200個程並べられ、労力が偲ばれた。
阿南の女性たちとその想いに協力した男性たち、企業、行政(市・県)が一体とならないと成立しない会議だったと思う。
徳島駅、朝7時半。駅前で旗を持ち案内してくれた女性達の笑顔、岡山から阿南までの往復の電車は会議参加者で満員だったが、隣合せた女性たちとの交流、全国から集まっているから情報が満杯。元気をもらった。
職場や家庭からDVをなくそうとしている男性たちが「相手を思いやると、自分にも返ってきます。」と言われたことは、足元を見直すことで男女共同参画は進んで、お互いが生きやすい世の中に変わっていくことに気づいたのだ。個性を大切に共生できる社会が広がることを願っている。
日本女性会議2012あなん参加報告

平成24年度男女共同参画市民研修「日本女性会議2012仙台」(平成24年10月26日(金曜日)から27日(土曜日))に参加しました。研修で全国の皆さんと交流しながら、女性の社会的地位の向上や男女共同参画の実践・実現について学んだことを報告します。
報告者 宇都宮とよ子(つつじケ丘)
学んだ内容のまとめ
大会のテーマでもあった「きめる」「うごく」「東北から」は、東北だけの問題ではなく、日本全体に関わる日常的な課題であると認識しました。女性自身が、自ら立ち上がり、声を上げなければ、「生存権」や「性の健康と権利」は守られないと学習できました。
参加の感想と今後について
仙台駅周辺と被災した沿岸部の格差は、今の日本の社会構造にもリンクするものがあり、考えさせられる思いでした。大会に参加させていただき、さまざまな人々と交流し、女性の強さを感じました。
学習した「情報」を一人でも多くの人と共有し、考え、伝えていかなければならないと強く感じました。
まさに「きめる」「うごく」「東北から」は、身近な私たちの生活の中にあると考えます。いつ起こるかわからない災害や困難に備え、連携し成長したいと思います。
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、左記の「Adobe Acrobat Reader」バナーをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 人権男女共同参画課 人権男女共同参画担当
電話:092-580-1840
ファクス:092-574-2053
場所:新館2階
